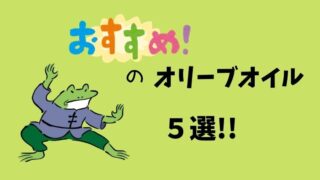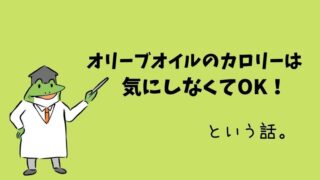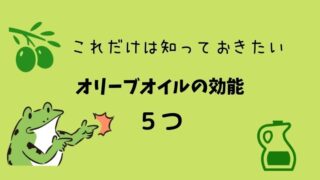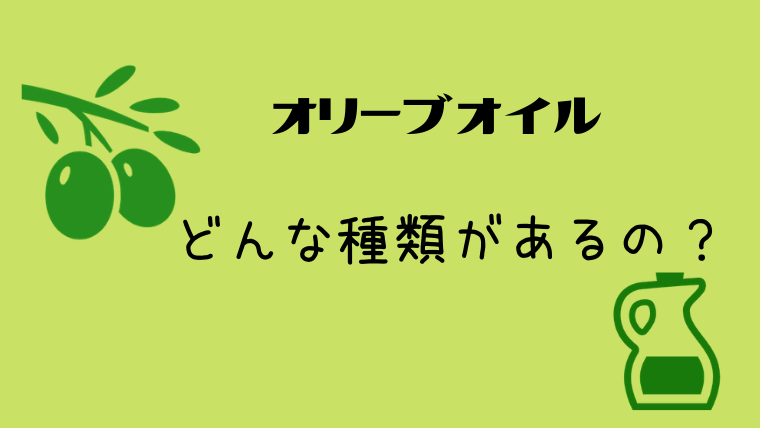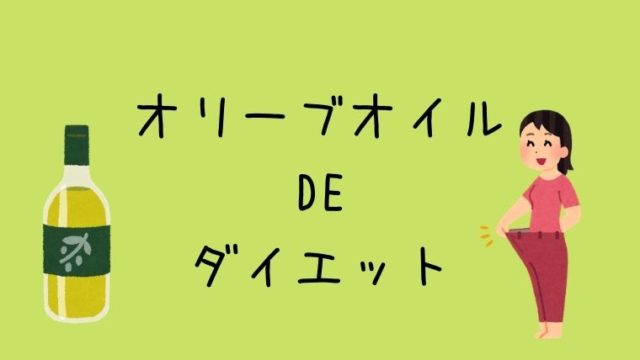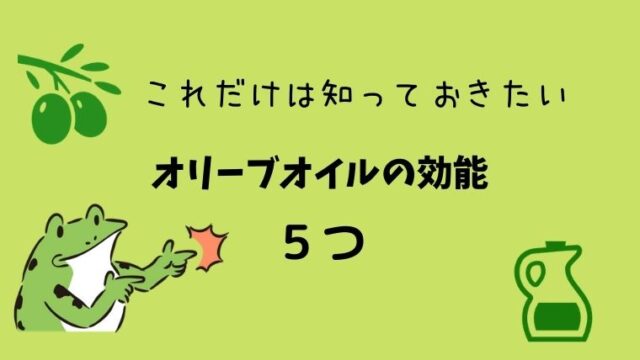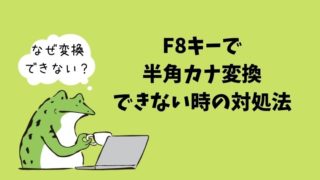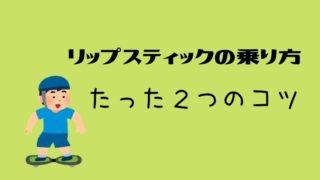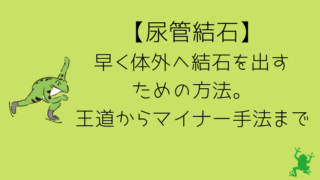オリーブオイルを毎日食べている、管理人のゆうきちです。
最近、日本でも健康ブームに乗っかって、オリーブオイルの人気が高まってきました。
中でもエクストラバージンオリーブオイルは特に人気が高いオリーブオイルの種類です。
しかし、巷では「日本で売られているエクストラバージンオリーブオイルは、ほとんどが偽物だ」と言う噂まで出ています。
何で偽物のエクストラバージンオリーブオイルが出回ってもお咎めが無いのか?
その謎は、実はオリーブオイルの国際規格と日本規格の違いにあったのです。
という訳で、この記事では、
に迫りたいと思います。
大ボリュームの内容ですが、最後までお付き合いを宜しくお願い致します。
Contents [hide]
オリーブオイルの国際規格

国際オリーブ協会という政府間機関が、スペインのマドリードにあります。
この国際オリーブ協会で、オリーブオイルの国際規格は作られました。
国際オリーブ協会は、通称IOC(International Olive Council)とも呼ばれます。
ちなみに、日本は国家としては、このIOCに加盟していません。
IOCへの非加盟国は、日本の他に、アメリカ、オーストラリア、ブラジル、ロシアなどがあります。
このIOC設立の歴史から、ヨーロッパの国々が中心となって作られた政府間組織のようですね。
IOCが定めたオリーブオイルの規格は、IOC公式サイトに掲載されています。
ただし、英語で書かれているので、英語が苦手な人はちょっと読みずらいです。
日本語に訳すと、このような感じになります。
まず、オリーブオイルは、4つのカテゴリに分類されます。
(1)バージンオリーブオイル
(2)精製オリーブオイル
(3)オリーブオイル
(4)オリーブポマースオイル
では、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
(1)バージンオリーブオイル
IOC公式サイトによると、バージンオリーブオイルの定義は以下の通りです。
バージン・オリーブオイルとは、オリーブ樹(Olea europaea L.)の果実から機械的または物理的な手段のみにより、オイルを変性させない条件下(特に温度条件)で得られたオイルであり、洗浄、デカンテーション、遠心分離、濾過以外の処理を経ていないものを指す。
つまり簡単に言い換えると、
オリーブの実を物理的に搾っただけの、オリーブ100%ジュースのこと
をバージンオリーブオイルと言います。
単なる100%オリーブジュースなので、オリーブそのものの味や香りが高く、人によってはクセが強過ぎて苦手! って人もいるようです。
でも、この「クセのある風味」が、バージンオリーブオイルの栄養価の高い理由であったりするので、一概にクセがあるからイヤッ! と言うのは非常にもったいないです。
ちなみに、オリーブを搾り取る時の工程は、日本酒や醤油を作る時の、もろみを搾る工程に近いようです。
物理的にオリーブの実を搾り取り、その後、不純物が沈殿するのを待つ工程なども含まれるため、とても手間暇が掛かります。オリーブオイルの中で最もフレッシュで高級なものの理由が分かりますね。
そして、バージンオリーブオイルの中でも、さらにランク付けされます。
バージンオリーブオイルの中でも、最も品質の高いのが、皆さんご存知の通り、エキストラバージンオリーブオイルです。
(1-1)エキストラバージンオリーブオイル
エキストラバージンオリーブオイルは、IOCによって次のように決められています。
遊離酸度がオレイン酸換算で100グラム中0.8グラム以下で、その他の特性が、IOC規格における当該カテゴリーに相当する特性と一致するオイル。
一般的によく言われる「酸度0.8%以下」がここで出てきます。
確かにいきなり「酸度」と言われても、なんとなく酸化しやすいことかな?
くらいしか思いつきません。
酸度とは、分かり易く言うと、
酸度は、新鮮なオリーブの実から作られたオリーブオイルかどうかを表す数値
です。
酸度が低いほど、フレッシュなオリーブの実を使った高品質なオイル、ということです。
少しだけ難しい話をしますと、油というものは、「グリセリン」というアルコールと、「脂肪酸」という酸が、化学的に結合したものです。
しかし、熱などによって、結合した脂肪酸が離れてしまうことがあります。
この離れてしまった脂肪酸の割合を表したものが、「酸度」です。
さらに深い話をします。
アルコールから離れてしまった脂肪酸は、空気中の酸素と結合しやすいという性質をもっています。
これが油の「酸化」です。
油が酸化すると、嫌な臭いを発生します。
質の悪い油が嫌な臭いを発生する理由は、この酸化が原因なのです。
話をオリーブオイルに戻しますと、つまり、
酸度が低いオリーブオイルは、酸化しにくいため、オリーブの実のフレッシュな香りやフルーティーな香りが続くので、酸度は低い方が美味しい。
と言うことなのです。
さて、ではなぜ酸度が低かったり高かったりしてしまうのでしょうか?
オリーブオイルを作る時には、大量のオリーブの実を一度に収穫して、一気にオイルを搾り取る作業に入ります。
しかし、その大量に収穫されたオリーブの実の中には、傷ついた実などが紛れ込んでいて、その傷ついた実から酸化が始まります。
これが酸度が高くなる原因です。
ですので、傷ついたり、腐ったりしたオリーブの実が少なければ少ないほど、酸度は低くなるのです。
ちなみにオレイン酸とは、油に多く含まれる脂肪酸のひとつで、実はオレイン酸という名前の由来も、オリーブオイルから発見されたことから命名されたようです。
ここで、オレイン酸についての余談ですが、オレイン酸は、一価の不飽和脂肪酸です。
ひまわり油やとうもろこし油、ごま油などに多く含まれる「多価不飽和脂肪(ω-6系)」は、発がん性物質や動脈硬化の疑いで、近年話題になっています。
それに対し、オリーブオイルに多く含まれるオレイン酸は、むしろ健康に良い効果で話題になっています。
それは、
悪玉コレステロール(LDL)の上昇を抑え、
さらに善玉コレステロール(HDL)の減少を抑えてくれる
という人間にとって健康に良い効果です。
オレイン酸の健康効果が、オリーブオイルの健康効果の源だったんですね。
オレイン酸についての雑学でした。
話を元に戻しまして、エクストラバージンオリーブオイルの基準についてです。
上で酸度が0.8%以下であればOK、と紹介しましたが、実はエクストラバージンオリーブオイルを名乗るには、さらにクリアしなくてはならない条件があります。
それは、
専門家による官能試験(人間の五感を使った試験)
です。
特別な訓練を受けた専門家10人前後による官能試験にも合格しなければならないのです。
この官能試験は、20項目にも及ぶようです。
オリーブオイルの色、におい、味(フルーティーさ、苦味、辛味)などを評価するようです。
実は、初めに紹介した「酸度0.8%以下」という基準は、意外と簡単にクリアできてしまう基準のようです。
なので、オリーブオイルの品質を見極める上で重要なのは、酸度よりも官能評価、つまり専門家によるテイスティングが最も重要と言われています。
エクストラバージンオリーブオイルを名乗るには、酸度0.8%以下の基準の他に、専門家による20項目もの官能試験に合格しなければならない。
ちなみに、エクストラバージンオリーブオイル以外のオリーブオイルの基準は、このように規定されています。
(1-2)バージンオリーブオイル
遊離酸度がオレイン酸換算で100グラム中2グラム以下で、その他の特性が、IOC規格における当該カテゴリーに定められた特性と一致するオイル。
バージンオリーブオイルは、遊離酸度が2%以下なので、エクストラバージンオリーブオイルよりもオレイン酸の純度が低いと言うことですね。
酸度が高いと、味や香りのクセも強くなってきます。料理によっては、エクストラバージンオリーブオイルよりも、バージンオリーブオイルの方が合う、なんてことも多いようです。
この辺のクセなんかは、色々と試してみないと分からないところがありそうですが、単純にエクストラバージンオリーブオイルだから一番美味しい! って訳でも無さそうです。
奥が深い! それがバージンオリーブオイルです。
(1-3)オーディナリーバージン・オリーブオイル
遊離酸度がオレイン酸換算で100グラム中3.3グラム以下で、その他の特性が、IOC規格における当該カテゴリーの特性と一致するオイル。
オーディナリーバージンオリーブオイルは、普通のバージンオリーブオイルよりも若干、不純物が多いと言うことですね。
(1-4)ランパンテバージン・オリーブオイル
遊離酸度がオレイン酸換算で100グラム中3.3グラムを超え、かつ(または)その官能特性が、IOC規格における当該カテゴリーで定められている官能特性を有するオイル。精製されるか工業用途に用いられる。
これは、食用に適さないオリーブオイルのことですね。
バージンオリーブオイルでも、食用に適さない物も出来てしまうようです。
(2)精製オリーブオイル
IOC規格によると、精製オリーブオイルは以下の様に定義されています。
精製オリーブオイルは、バージン・オリーブオイルから、当初のグリセリド構造の変化につながらない精製法によって得られたオイル。 遊離酸度がオレイン酸換算で100グラム中0.3グラム以下で、その他の特性が、IOC規格における当該カテゴリーに定められている特性と一致するオイル。 このカテゴリーのオイルは、小売りが行われる国において、法的な許可がある場合にのみ、消費者に販売される。
意外にエクストラバージンオリーブオイルの酸度0.8%以下よりも低いんだな。
精製オリーブオイルは、バージンオリーブオイルのように物理的にオリーブの実を搾り取っただけの製法ではありません。
精製とは、抽出したオリーブオイルには多くの不純物が混ざっており、臭いや色を整えて美味しく食べられるレベルまで品質を上げるため、物理的や化学的にこれらの問題を対策して、美味しいオリーブオイルにする工程のことを言います。
具体的には、脱ガム、脱臭、脱酸、脱色などを行うようです。
この時、水酸化ナトリウムを使って遊離脂肪酸を取り除いたりするので、酸度は必然的に下がってしまいます。
なので、「酸度が低いからオリーブオイルの品質が良い」という訳ではないのです。
酸度を下げるのは、精製すると比較的簡単にできてしまう、と言うことです。
ちなみに、酸度が下がることで、オリーブオイルの風味や栄養素も同時に失われてしまうので、基本的には、
精製オリーブオイルは、バージンオリーブオイルに比べて栄養価は低くなる
のが一般的なようです。
精製オリーブオイルは、酸度が低く、クセもなくサラッとしているので、日本人にとっては食べやすい油なのかもしれません。
しかし、食べやすく、クセが無い反面、本来オリーブオイルが持っている優秀な栄養価まで失われているようなのです。
私も以前はそうでしたが、日本では油に風味や臭いなどのクセがあるのを嫌うことが多いような気がします。
元々、サラダ油などの無味無臭の油を日常で食べていたので、油にクセがあるのは品質の悪い油だ! みたいな先入観があるのかも知れません。
しかし、オリーブオイルは、普通の油とは異なる食材だと思った方が良いかもしれません。
調味料としても使えるし、何よりバージンオリーブオイルの栄養価はとても高く、健康効果も非常に高いです。
という訳で、オリーブオイルを食べるなら、せっかくなので、ちょっとクセのあるバージンオリーブオイルを試してみてはいかがでしょう?
(3)オリーブオイル
3つ目は、単なるオリーブオイルです。
IOCによると、
オリーブオイルは、精製オリーブオイルとバージン・オリーブオイルをブレンドしたオイル。遊離酸度がオレイン酸換算で100グラム中1グラム以下で、その他の特性が、IOC規格における当該カテゴリーの特性と一致するオイル。国によっては、より具体的な呼称が求められる場合がある。
要は、バージンオリーブオイルと精製オリーブオイルを少しでもブレンドしたら、それは普通のオリーブオイル、と言うことですね。
(4)オリーブポマースオイル
最後に紹介するのは、オリーブポマースオイルです。
オリーブポマースオイルは、オリーブポマースを溶剤もしくは他の物理的方法で処理して得られたオイルであり、再エステル化プロセスで得られたオイルや別の種類のオイルと混合されたオイルを除く。販売にあたっては、以下の呼称と定義に従う。
オリーブポマースオイルは、オリーブオイルの搾りかすを再度、溶剤を使って油を搾り取ったもので、オリーブオイルと言う名称で売ることを禁止されています。
オリーブポマースオイルの用途としては、バージンオリーブオイルよりも発煙点が高いものが多く(およそ230~240℃)、揚げ物などに適している油のようです。
逆にサラダ用のドレッシングなど、生で食べるのは控えた方が良さそうですね。
オリーブポマースオイルは、安い材料で作られているだけあって、お値段はとても安いです。
安いオリーブオイルを発見したら、まずはそれがオリーブポマースオイルかどうかを確認するのが良さそうです。
日本のオリーブオイル基準
世界のオリーブオイル基準に続いて、次は日本のオリーブオイル基準を紹介したいと思います。
上でも紹介しましたように、日本は世界オリーブ協会(IOC)へ加盟していません。
なので、日本独自のオリーブオイル基準が存在します。
日本のオリーブオイル基準は、農林規格(JAS)によって定められています。
食用植物油脂の日本農林規格、第13条に「食用オリーブ油の規格」という項目が規定されています。
この規格を見ると、日本基準と世界基準が大きく違うことが分かります。
日本と世界でどれくらい基準が違うのかと言いますと、例えば世界基準であるIOC規格では、オリーブオイルは、4つの大分類、
(1)バージンオリーブオイル
(2)精製オリーブオイル
(3)オリーブオイル
(4)オリーブポマースオイル
に分けられ、さらに(1)のバージンオリーブオイルは、4つの中分類、
(1-1)エクストラバージンオリーブオイル
(1-2)バージンオリーブオイル
(1-3)オーディナリーバージン・オリーブオイル
(1-4)ランパンテバージン・オリーブオイル
まで細かく分かれています。
これに対し、日本のオリーブオイル基準は、たったの2つしか存在しません。
(1)オリーブ油
(2)精製オリーブ油
この日本の農林規格(JAS)は、1969年に設立されたとても古い規格なので、当初はオリーブオイル自体、日本にほとんど存在していなかった油だったからかも知れませんね。
近年は、オリーブオイルの健康効果が日本でも注目を集めているので、近い将来、日本のオリーブオイル基準も見直されるかも知れませんね。
ひとまず、2020年現在の日本のオリーブオイル基準を紹介したいと思います。
(1)オリーブ油(オリーブオイル)
JAS規格13条によると、世界基準であるIOC規格の「酸度0.8%以下」に相当するのは、
酸価2.0以下であること
の部分です。
ちなみに、「酸価」と「酸度」は、よく似ていますが異なる指標です。
酸価から酸度に換算するには、
酸度=酸価×0.503
という計算方法で換算できます。
つまり、日本基準の「酸価2.0以下」は、世界基準へ換算すると「酸度1.006%以下」に相当すると言うことです。
知らない人が見ると、日本基準は「酸度2.0%以下」なのか! と勘違いしそうだ。
これは実際、勘違いしている人が多そうですね。
さらに日本の基準では「オレイン酸」を分母に換算するなどの条件が無いので、細かい部分はいろいろと違いそうです。
ちなみに、JAS規格の食用植物油脂には、酸価の試験方法も記載されていますが、5分悩んで理解するのを諦めました…。
日本基準のオリーブオイルと精製オリーブオイルの違いを見てみると、たった3つしか違いがありませんでした。
1つ目は、先ほど紹介した「酸価」の値です。
2つ目は、オリーブオイルの「一般状態」に関してです。
| オリーブオイル | 精製オリーブオイル | |
| 一般状態 | オリーブ特有の香味を有し、おおむね清澄であること。 | おおむね清澄で、香味良好であること。 |
これを見る限り、「オリーブ特有の」香りがあるか無いかで区別するようですね。
「オリーブ特有の」って、なに?
知る人ぞ知る何かなんですかね?
なんとなく、オリーブオイルは香りがある程度あって、精製オリーブオイルは香りがほとんど無い。みたいなことを言いたいような気もします。
実際、精製されたオリーブオイルは、クセが無くて香りもほとんどしないので、きっとそう言うことなのでしょう。
ざっくりしてるなー、JAS規格。
ちなみに、3つ目の違いは、「水分及びきょう雑物」という項目でした。オリーブオイルが0.30%以下で、精製オリーブオイルが0.15%以下であることが条件のようです。
あと、日本のJAS規格を読んでみると、気になる項目として、
色: 特有の色であること。
とあります。
何? 特有の色って…。
こんな曖昧な基準があるのも、JAS規格が制定されたのが古くて、まだ誰もオリーブオイルを知らなかったから、適当に決めちゃったのかも知れませんね。ここの項目も、きっと近い将来、基準を見直されるでしょう。
あと、日本のJAS規格でこれは良いな! と個人的に思ったのが、
添加物: 使用していないこと。
という項目です。
他のひまわり油やパーム油など、ほぼ全ての油で添加物の使用が規定値以内であれば許可されていますが、オリーブオイルだけは、
添加物は使っていけません!
となっています。
なぜオリーブオイルだけ特別扱いされているかは分かりませんが、この添加物は使ったらNG! という項目はとても評価できますね。
少なくとも、日本で販売されているオリーブオイルは、添加物不使用という訳です。
これだけでも他の油を使うよりは、オリーブオイルの方が健康に良いと言えそうです。
日本で販売されているオリーブオイルは、添加物を使用していない。だから他の油よりオリーブオイルは、健康効果が高い。
(2)精製オリーブ油(精製オリーブオイル)
次に、精製オリーブオイルの日本基準です。
酸価0.6以下であること
とあるので、世界のIOC基準に換算すると、「酸度0.3018%以下」に相当します。
しかし、酸度が低いからと言って、IOC基準のエクストラバージンオリーブオイルのような高品質である訳ではありません。上で世界基準の精製オリーブオイルでも紹介したように、精製する工程では、簡単に酸度が下がってしまうためです。酸度が下がって、同時にオリーブオイルの栄養価も失われてしまうので、やはり理想は精製されていないバージンオリーブオイルを頂くのが良いですね。
ちなみに、精製オリーブオイルは、日本では、
ピュアオリーブオイル
なんて名前で売られていたりもします。
「ピュア」とか言われると、どことなく品質が良さそうな感じがしますが、実際は精製されたオリーブオイルを使っているので、IOC基準のバージンオリーブオイルよりも品質は劣ります。
名前に惑わされないように注意したいものです。
日本基準の精製オリーブオイルの用途は、世界基準の精製オリーブオイル同様、炒め物や揚げ物に使うのが良さそうですね。
まとめ|オリーブオイルの国際規格
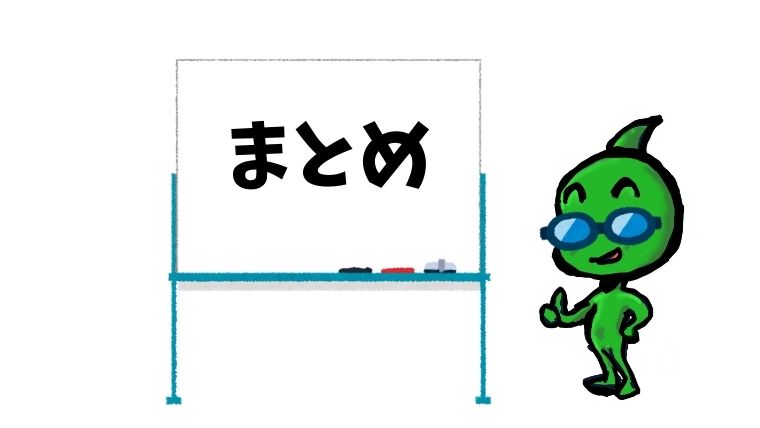
オリーブオイルの国際規格について紹介しました。
オリーブオイルの種類と基準は、世界基準と日本基準でこんなにも違うんだ! と言うことを分かって頂けたと思います。
国際規格の国際オリーブ協会(IOC)が規定した基準によると、オリーブオイルの種類が大分類で4種類、その内、最も高品質なバージンオリーブオイルの分類でも4種類に分けられることが分かりました。細分化された中でも、最も高品質なのがエクストラバージンオリーブオイルと言うことが分かりました。
一方、日本のオリーブオイル基準はと言うと、日本農林規格(JAS)の第13条にオリーブオイルの規定がありました。しかし、JASにはたったの2種類しか分類が無く、オリーブ油と精製オリーブ油しか規定がありませんでした。なので、日本でオリーブオイルを販売する場合、オリーブ油の規定である「酸価2.0以下(酸度1.006%以下に相当)」と「オリーブ特有の香味」さえあれば、例えば「エクストラバージンオリーブオイル」とうたっても何の問題も無いのです。
今回のオリーブオイルの調査で個人的にひとまずこれだけは言えそうだな。と思ったのが、
IOC基準のバージンオリーブオイルを選ぶ
これが最も賢いオリーブオイルの選び方だと思いました。
味の良し悪しやクセの強さなど、様々な違いはありそうですが、バージンオリーブオイルと精製オリーブオイルでは、栄養価に大きな差があります。
搾りたての100%ジュースであるバージンオリーブオイルを購入するようにすれば、エクストラバージンで無くても良いかも? と思った次第であります。
あとは個人の味の好みですね。
皆さんも自分好みのバージンオリーブオイルを見付けて、健康的な身体を保てると、人生がさらに楽しいものになると思いますよ。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
<本記事の参考にした資料>
・国際オリーブ協会(IOC)公式サイト(https://www.internationaloliveoil.org/)
・「医者が教える食事術」牧野善二著(ダイヤモンド社)