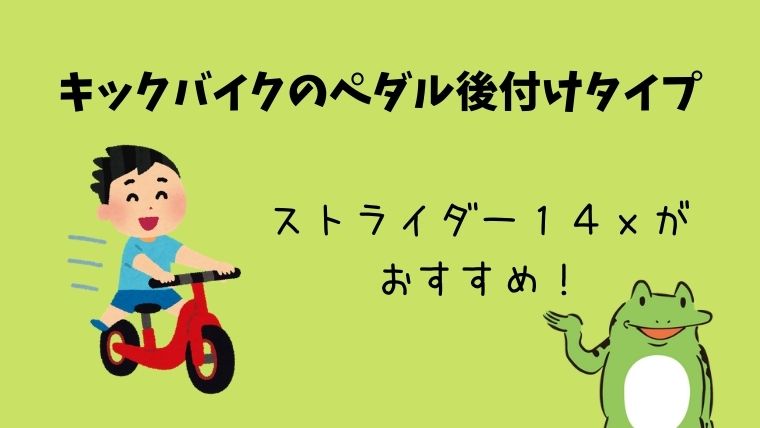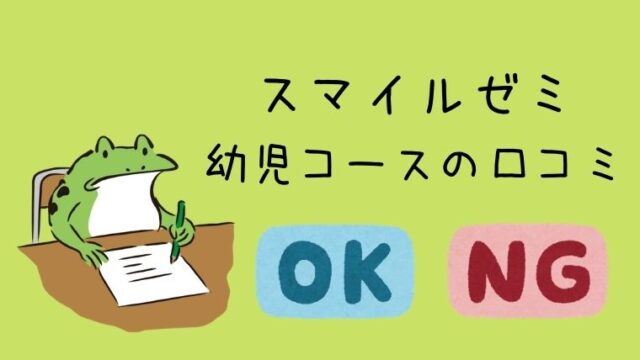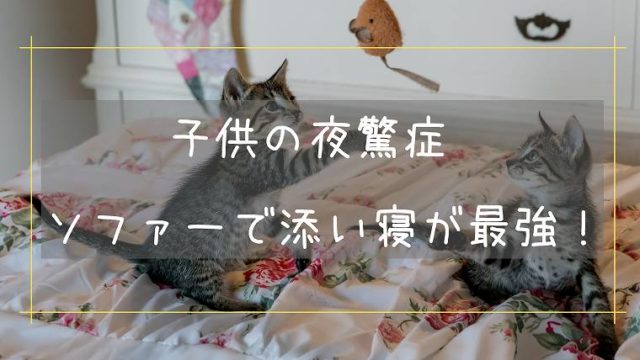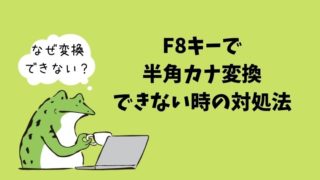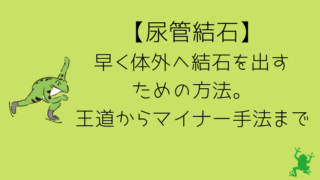最近、幼稚園の娘が自転車に補助輪なしで乗れるようになりました。
親バカなところも多々あると思いますが、たった3日で乗れるようになりました。
たった3日で乗れるようになったことを詳しく紹介した記事は、こちら↓

上の記事でも紹介しましたが、早く自転車に乗れるようになるには、2歳半から乗り始めたキックバイクの存在が大きいと考えています。
そこで今回は、
について紹介したいと思います。
特に人気の高い「ストライダー14x」についても紹介します。
では、始めましょう。キックバイクのペダル後付けタイプのおすすめは?
Contents [hide]
キックバイクのペダル後付けタイプ

初めに結論からですが、
「ストライダー14x」がおすすめ
です。
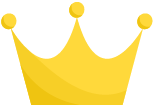 ランキング1位
ランキング1位
キックバイクの代名詞、ストライダー社が手掛ける「ストライダー14x」。
やはり「ストライダー」のロゴが入ると、公園でもひときわ目立ちます。
外観のカッコ良さはストライダーならではです。
ストライダー14xは、タイヤが14インチのペダル後付けが可能なキックバイクです。
ブレーキも付いていて、さらに2年間の保証付きです。
幅広いユーザに支持されている文句なしにおすすめのキックバイクです。
| メーカ | ストライダー |
|---|---|
| 重量 | 5.5kg(ランニングバイクモード)→6.5kg(ペダルバイクモード) |
| ブレーキ | あり |
| タイヤ | EVA製 |
| 対象年齢 | 3歳半~7歳 |
ストライダー社製キックバイクの評判

日本では、圧倒的にキックバイクではストライダー社の知名度が高いですが、当然、ブランド力が高いと値段も跳ね上がります。
ここでは、
について紹介したいと思います。
価格面で比較すると、この通り。
| ストライダー | DABADA | santasan | ヤトミ | |
| 価格 | 1万円~ | 4,998円 | 4,580円 | 5,940円 |
| ブレーキ | なし | あり | あり | あり |
| タイヤ | EVA | EVA | EVA | EVA |
ブレーキが無い仕様にも関わらず、価格面でも圧倒的にストライダーが高価です。
ストライダーの場合、少し種類を選ぶと、簡単に2万円台を突破してしまいます。
口コミ評価も調べてみると、ユーザ満足度は総じて高く、
amazonのクチコミ評価でも、ストライダー製のキックバイクはどれも高めです。
一方、ユーザの満足度としては、1万5000円のストライダーも、6000円弱の他社製のキックバイクも、満足度の高いキックバイクの種類はそれぞれです。
ストライダー社製を選ぶひとつの理由としては、
「ストライダーカップ」に出場するには、ストライダーでなければいけない
というのがありそうです。
ストライダーカップは、全国各地で行われています。
私も以前、茶臼山という観光名所行った際、偶然ストライダーカップが開催されていましました。
開催地は、山奥だというのに、多くの出場者の子供でにぎわっていたのを覚えています。
ストライダーカップに出て、レースを楽しみたい!
という方は、是非ストライダーを買って、子供達と楽しい思い出を作って下さい。
ストライダーカップに偶然居合わせた際の記事は、こちら↓

キックバイクとは?
ここでは、キックバイクの基礎を紹介します。
キックバイクについて詳しい方は読み飛ばして下さいね。
キックバイクとは?
自転車のようにまたがって乗り、足で地面を蹴って進む、ペダルのない幼児用の乗り物。子供用ペダルなし自転車とも言える。日本では、様々な呼び方があり過ぎて混乱しやすい。(現に私が混乱していた)
キックバイクの呼び方は、以下のようなものがあります。
| キックバイク | 日本における一般的な呼び方。 |
| バランスバイク (balance bike) |
英語など、世界で一般的に使われる呼び方。日本では、ラングスジャパン社の商標。 |
| ストライダー (strider) |
キックバイクメーカである米国Strider Sports International社の名称。日本全国でストライダー社は、レースイベントを主催など活動している。日本で最も有名なキックバイクメーカ。日本における商標は、株式会社Ampus(旧株式会社豆魚雷)が持っている。Ampusは、ストライダージャパンというブランドでストライダーを輸入販売している。米ストライダー社の子会社に当たるのかな? |
| ランニングバイク | 株式会社Ampus(旧株式会社豆魚雷)の商標。 |
| ペダル無し自転車 | 通販などの広告で使われるフレーズ。 |
| ペダルなし二輪遊具 | 日本の消費者庁などの行政の文書で使われている名称らしい。一般人は絶対に使わないだろう…。 |
日本では、上記の他に、「キッズバイク」「トレーニングバイク」「ランバイク」など様々な呼称が使われます。
ややこしいですねー。
上の表から分かるように、日本でよく使われる「ストライダー」という単語は、単にキックバイクのメーカ名なので、会話で使う場合は、一般名称である「キックバイク」の方が適切な使い方です。
以上、細かい話でした。
キックバイクの選び方
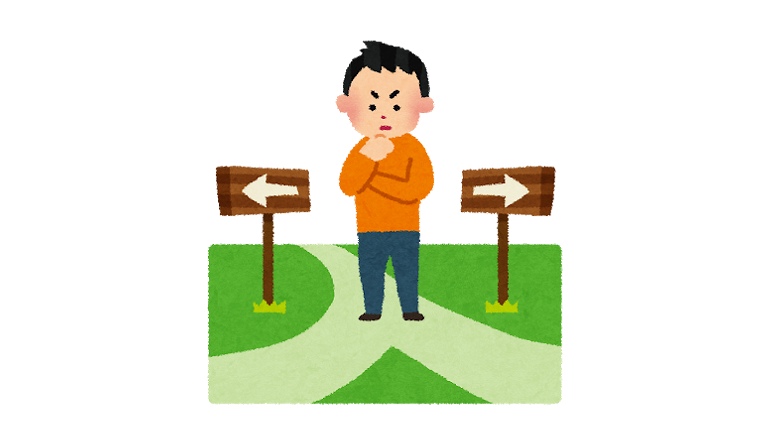
結論から言いますと、
ペダル後付けタイプのキックバイク
をおすすめします。
理由は、
ペダル後付けタイプのキックバイクの方が、トータルでみるとコスパが良いため
です。
子供が自転車に乗るまでの間、幼稚園から小学1年生くらいまでの間に、ほとんどのご家庭は、
キックバイク1台+自転車1台
を買います。
単純に言ってしまうと、このキックバイク1台+自転車1台を、1つにまとめてしまうのがペダル後付けキックバイクです。
正直なところ、キックバイクの性能としては、どのメーカを使っても大差ないと思います。
しかし、自転車練習をそのまま継続してできるメリットは、ペダル後付けタイプだけが持つ強みです。
ちなみに、キックバイクが自転車練習に有効な理由は、
バランス感覚を遊びながら自然に養うこと
ができるからです。
だから、最低限、車輪が2個ついて、足で地面を蹴って、前に進めさえすれば、自転車練習には効果を発揮します。
ただし、粗悪品をつかまされるリスクだけは注意が必要です。
メーカ不明で中国製の粗悪品1500円なんてのもセール品で出回ることがありますが、耐久性が悪かったり、サドル調整を考えないお粗末な設計だったりと、後で大変苦労します。
なので、個人的には、ストレスを感じるくらいなら、価格は上がりますが、初めからストライダーのような素性の分かるメーカの品質保証の付いたランクのキッズバイクを選ぶことをおすすめします。
ちなみに、我が家も初めて購入したメーカ不詳、中国製1500円くらいで購入したキッズバイクは、結果的にとても無駄な買い物になってしまいました。
値段が安いものは、安いなりの理由があるということだな。
サドルの向きが簡単に変わってしまったり、六角レンチを使わないと微調整をできなかったり、ハンドルのグリップ部分のゴムが割れたりと、散々な目に遭いました。
結果、解体して燃えないゴミ行となりました…。
こういうことになるくらいなら、初めからストライダーを買っておけば良かった。と思いますよね。たとえ安くても、1500円をドブに捨てることになるのですから。
メーカ不詳で中国製などの粗悪品を買うと、後で買い直す羽目になる可能性が高いので、注意が必要。
初めから、ストライダーのような素性の分かるメーカー品を買うのが賢い買い物。
キックバイクの選び方1:ブレーキの有無はどちらでもOK
我が家では、ブレーキ無しのキックバイクを乗っていましたが、ブレーキ付きを買っていればと少し後悔しています。
理由は、
ブレーキが無かったために、子供が怪我をしたため
です。
公園内でキックバイクで遊んでいた時のこと、公園から帰る時、出入り口の坂でそれは起こりました。
下り坂を猛スピードで下って、道の脇の木に激突したのです。
一瞬の出来事だったので、私も対処できませんでした。
キックバイクの運転に慣れてくると、簡単にスピードを出せるようになります。
平坦な場所であれば、それなりに子供も感覚が養えるので、これくらいのスピードなら止まれるスピードだ、と、本人も制御できますが、問題は下りの坂道です。
本人の予想を超えたスピードがいとも簡単に出てしまうのです。
それほど大きな事故にはならなかったので良かったのですが、子供にしては可哀そうな打撲と擦り傷を付けてしまいました。
親としては後悔すべき出来事でした。
しかし、その木に激突事件の後、一度も激突するような事故は起きませんでした。
子供は子供なりに学習しているようで、その日以来、スピードを出さなくなったのです。
という訳で、個人的には、ブレーキはあるに越したことはありませんが、無くても無いなりに楽しめるますが、おすすめはやはりブレーキありのキックバイクです。
キックバイクは、ブレーキ付きがおすすめ。
(ただし、無くても何とかなります。多少の怪我はしてしまいますが…)
注意点として、もうひとつ。
ブレーキありのキックバイクを買っても、手の大きさと握力が足りないと、ブレーキを使うことは難しい場合があります。
キックバイクを使い始めるのは、早い子で2歳からとなりますが、2歳ではさすがにブレーキは使用できません。
参考ですが、現在5歳の我が家の娘は、普通にブレーキを使えます。
なので、使えるようになるのは3歳~4歳くらいだと思われます。
メーカや型番によって、使いやすいブレーキ、使いにくいブレーキもあると思いますので、すぐに使いたい場合は、実際にお店でブレーキを使えるかを試してみると確実ですね。
ストライダー14xは3歳半からなので、ブレーキも使える子が多いと思います。
キックバイクの選び方2:スタンドは無くてもOK
自転車感覚で考えると、自立させられるスタンドは、必須のように思えてしまうかもしれませんが、キックバイクに関しては、スタンドは必要ありません。
理由は、キックバイクの体格が自転車に比べて極めて小さく、極めて軽いため、壁に立てかけておくだけで安定するからです。スタンドが無くて困ったことは、一度もありませんでした。
なので、もしお金に余裕があって、キックバイクを使っていない状態で、見栄えを気にされる場合など以外は、不要、と考えてOKです。
でも、最近のキックバイクは、スタンドが無料で付いてくることも多くなりました。
特にストライダー14xなどの高級なクラスは、できれば傷を付けたくないので、別売りのスタンドを買っても良いと思います。
一般的には、キックバイクにはスタンドが無くてもOK。
ただし、ストライダー14xのような高級モデルには、傷つき対策でスタンドを付けたいところ。
キックバイクの選び方3:タイヤの種類(ゴム、EVA)は気にする必要なし
タイヤの種類も、気にする必要はありません。
タイヤの種類は、ゴム製とEVA製(※1)があります。
(※1:EVAとは、水を吸わない柔らかい性質を持つ合成樹脂で、サンダルの底やバスマットなどに使われている素材です。ウレタン製とも言います。)
メリットとデメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット | |
| ゴム製のタイヤ | ・タイヤが滑りにくい(グリップ力がある) | ・パンクする可能性がある。 ・空気圧をチェックする手間がかかる ・少し重い ・少し高価 |
| EVA製のタイヤ | ・パンクしない(空気を入れる必要なし) ・少し軽い ・少し安価 |
・タイヤが若干滑りやすい |
安全面から、グリップ力のあるゴム製タイヤの方がおすすめですが、EVA製タイヤでも特に問題ありません。
我が家は、EVA製タイヤの方を使用していました。
確かにアスファルト上では、グリップ力に違いが出ますが、ほとんどの場合、遊ぶ場所は公園などの土の上です。
もともと土の上は、滑りやすいので、ゴム製もEVA製も大差ないと思いました。(ゴム製でも土や砂の上ではグリップの利きが悪いです)
タイヤの種類は、ゴム製でもEVA製でも、どちらでもOK
キックバイクの選び方4:ペダル後付け機能は、あった方が良い
キックバイクの種類によっては、高価なグレードでペダル後付けできる物もあります。
後付けペダルは、キックバイクで遊ぶ分には無くても全然OKです。
しかし、自転車練習を兼用したいのであれば、ペダル後付けタイプをおすすめします。
理由は、上の方でも紹介した通り、スムーズな自転車練習への切り替えが可能で、さらに幼稚園から小学1年生くらいまで1台のキックバイクでまかなえてしまいます。
つまり、コスパは最高に良いです。
普通のご家庭では、キックバイク1台を幼稚園で買い、小学校へ上がる前に自転車を1台買います。このキックバイクと自転車を合わせた2台分の役割を果たしてくれます。
子供の成長は早いので、初めに買った自転車は、小学2年生から3年生には使えなくなってしまい、新しい2台目の自転車を買うことになるので、結果的にはペダル後付けタイプのキックバイクがコスパが良い訳です。
キックバイクは、ペダル後付けタイプがおすすめ。
ペダル後付けタイプなら、スムーズに自転車練習へ移行できます。
【コスパ重視】ペダルなしキックバイク3選!

ここまではペダル後付けタイプをおすすめしてきましたが、やっぱりペダルなしのキックバイクも見てみたい! そんな方におすすめのキックバイクを紹介します。我が家で使ってきたキックバイクの経験から、重要なポイントを抑えて、後悔しないキックバイクを選定しました。
特にペダルなしでコストパフォーマンスの良い点を重視して選びました。
当然、高いお金を払えば性能の良いキックバイクも買えますが、ここではコスパ重視の観点から、高価なクラスは除外しました。
選ぶときの参考にして頂ければと思います。
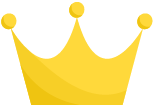 ランキング1位
ランキング1位キックバイクの代名詞「ストライダー」の外観に負けず劣らずのカッコ良さが印象的なキックバイクです。ブレーキ付き&スタンド付きで、破格の値段です。幅広いユーザに支持されているキックバイクです。(この商品名は、バランスバイク)。今なら、さらにプロテクター(膝、肘、手)も付いて、価格はそのままです。今、イチ押しのコスパ最強キックバイクです。
| メーカ | DABADA |
|---|---|
| 重量 | 約4kg |
| ブレーキ | あり |
| タイヤ | EVA製 |
| 対象年齢 | 2歳~5歳 |
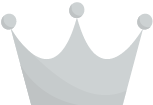 ランキング2位
ランキング2位キックバイクの設計を日本が担当し、生産のみ中国という仕組みでこの安価を実現した、コスパ最高のキックバイク「公園の天使」です。おしゃれなデザインと、前カゴも付いたデザインが、女の子にピッタリのキックバイクです。ブレーキとスタンドも付いて、この値段。
| メーカ | santasan(サンタサン) |
|---|---|
| 重量 | 約3.5kg |
| ブレーキ | あり |
| タイヤ | EVA製 |
| 対象年齢 | 2歳~5歳 |
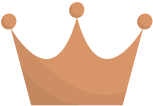 ランキング3位
ランキング3位平衡感覚のバランスを取りやすいと評判のキックバイク「モンキーバイク」。バランスを取りやすい安定感の理由は、そのタイヤの太さ。幅が6cmもあるワイドタイヤを採用しています。価格もとてもリーズナブルです。スタンドも付いています。
| メーカ | ヤトミ |
|---|---|
| 重量 | 2.5kg |
| ブレーキ | なし |
| タイヤ | EVA製 |
| 対象年齢 | 2歳~ |
まとめ|キックバイクのペダル後付けタイプ
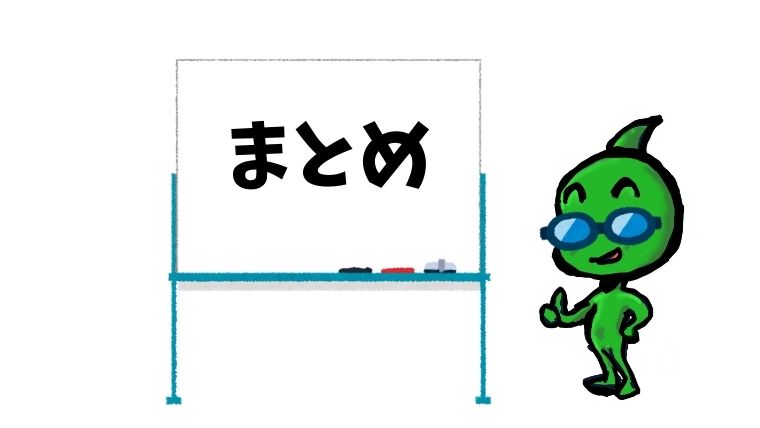
キックバイクのペダル後付けタイプについて紹介しました。
また、キックバイクの選び方についても紹介しました。
キックバイクのペダル後付けタイプのおすすめは、ストライダー14xです。
ペダル後付けタイプは、スムーズに自転車練習へ移ることができます。
また、ストライダー14xを持っていると、全国各地で開催されているストライダーカップに出場することもできます。
これからのお子さんとの楽しいキックバイクライフを!
\ おすすめです! /
\ ヘルメットの購入もお忘れなく! /
キャスターボードの乗り方のコツに関する記事はこちら↓
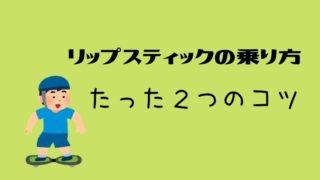
自転車練習のできる交通公園ってどんなところ?
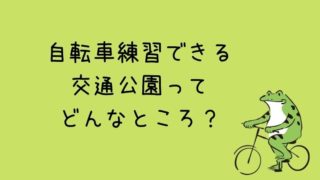
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。