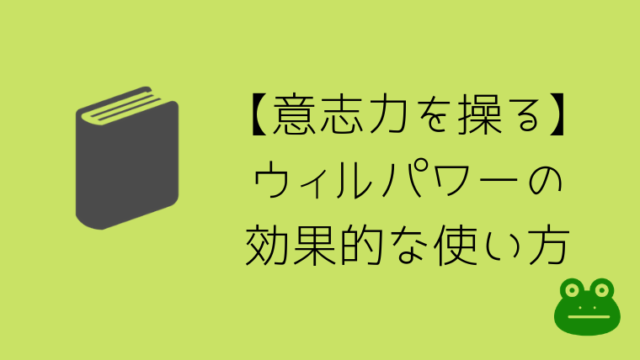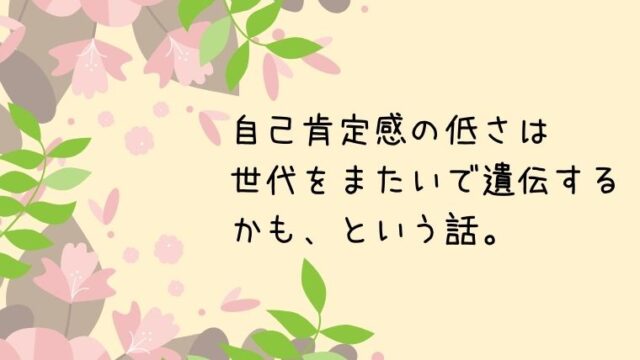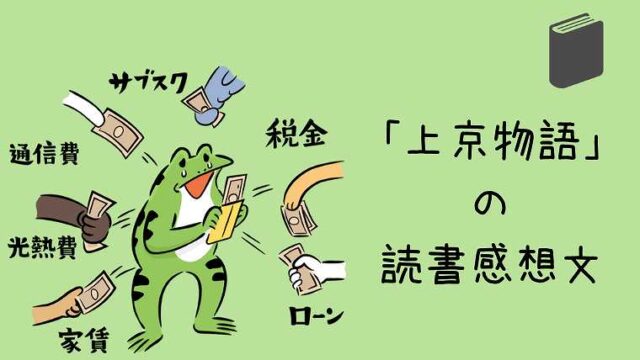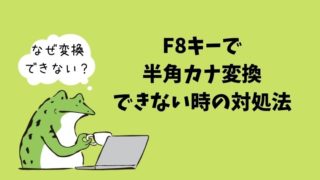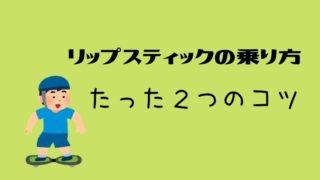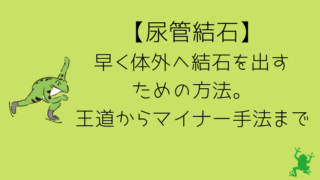【本】「手紙屋」の名言|1作目と2作目をまとめてお届け!

こんにちは、管理人です。
今回は、「手紙屋」の名言をお届けします。
「手紙屋」は、1作目の「手紙屋~僕の就職活動を変えた十通の手紙~」と、2作目の「手紙屋 蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙」があります。
本記事では、2つの作品の名言を合わせて紹介します。
この記事を読むと、こんなことが分かります。
- 「手紙屋~僕の就職活動を変えた十通の手紙~」の名言が分かる。
- 「手紙屋 蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙」の名言が分かる。
なお、2作品ともに題名がとっても長いので、誠に勝手ながら以下のように省略させて頂きます。
- 1作目:「涼太の就職活動編」
- 2作目:「和花の受験勉強編」
では参りましょう。「手紙屋」の名言、1作目と2作目を合わせて紹介!
- タイトル: 1作目「手紙屋~僕の就職活動を変えた十通の手紙~」、2作目「手紙屋 蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙」
- 著者: 喜多川泰
- ジャンル: 自己啓発、文芸(教養小説)
- 出版年: 1作目2007年、2作目:2007年
- 出版社: ディスカヴァー・トゥエンティワン
\ 初めての方は30日間無料! /
解約も簡単にできます。
「手紙屋」もプレミアムプラン(月額1500円)なら無料で読める! しかも初めての方は30日間の無料体験あり! もちろん、30日以内に解約すれば月額1500円も支払わなくてOK! 解約もスマホ1つで簡単にできる!
※本記事は、2025年現在の情報を元に書いています。最新の情報については、AmazonまたはAudible公式サイトをご確認ください。
この記事は、こんな人が書いています。
- 「手紙屋」シリーズが好きな人
- 喜多川泰さんの本が好きな人
- 素晴らしい本との出会いで人生を豊かにしたい人
「手紙屋」の読書感想文は、こちら↓
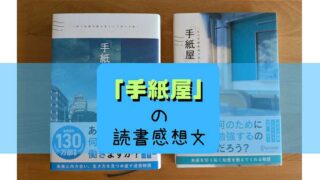
Contents
涼太の就職活動編
手紙屋の名言_涼太の就職活動編.jpg)
「手紙屋」の名言、はじめに1作目の「手紙屋~僕の就職活動を変えた十通の手紙~」から紹介します。1作目は、本のタイトルでも分かる通り、就職活動で悩む若者が主人公の物語です。就職活動、つまり「働くこととは?」に焦点をあてた物語です。
就職活動中ではなくても、すでに働いている人にも、心に刺さる名言が盛りだくさんです。
なお、本に登場する名言の解釈については、人によって様々です。本記事では、管理人の解釈を紹介しておりますが、この解釈が数ある解釈の中のひとつの意見と思っていただけると幸いです。
(1)「物々交換」
涼太へ贈る手紙屋の名言、1つ目は「物々交換」です。
現代の日本に住んでいたら気付きにくい、というか気付かないことがほとんどではないかと思うくらい。私たちは、「物々交換」と縁のない生活をしているかのように思います。もちろん、現代人が物を手に入れる手段の基本は、お金ですよね。しかし、手紙屋は、現代でも「物々交換」が基本である、と言います。
手紙屋は、確かにお金でも交換はするけど、あくまでも「物々交換」で成り立っている。そう主張します。
”『相手の持っているものの中で自分が欲しいものと、自分が持っているものの中で相手が欲しがるものとを、お互いがちょうどいいと思う量で交換している』”
現代の日本では、お金で物を購入するので、物々交換の表現にすると、こうなります。
例えば、本屋さんで本を購入する場合。
本屋さんとお客さんは、「1冊の本」と「それに見合うお金」を物々交換する。
例えば、会社で働くサラリーマン(従業員)の場合。
会社と従業員は、「1か月分の給料」と「1か月分の時間および労働力」を物々交換する。
手紙屋は、自分が差し出す物は、お金以外にもたくさんあることを知ることが大事だと言います。
あなたが持っているお金以外の魅力的な物。
- 時間
- 労働力
- 知識
- 経験
その他にも考えればいくらでも出てくる。
周りの人が欲しがるもの。
同様にあなたが会社から欲しい物は、お金や安定だけでしょうか?
世の中、お金だけが全てではない。
本質は、物々交換。
それを覚えておくだけで、視野が格段に広くなると思いませんか?
「物々交換」: お金だけが全てではない。あなたは周りの人が欲しがる魅力的なものを持っていることを忘れてはいけない。
(2)「あなたの称号」
2つ目の名言は「あなたの称号」です。
手紙屋は、あなたの周りの人を全てあなたの味方にしてしまう魔法の言葉を教えてくれます。
”相手にこうなってほしいという『称号』を与えてしまうのです。”
例えば、相手に「あなたはとても心の優しい人だ」と称号を与えると、その相手は、あなたの前では優しい人であろうと努力する。
もし、あなたの周りでいつもイライラして怒ってばかりいる人がいたら、「あなたは本当は心の優しい人なんですね」と一言伝えるだけで、ずいぶん態度が変わるかもしれません。
「あなたの称号」: 相手に称号を与えると、相手はその称号にふさわしい行動を取るようになる。
(3)「天は自ら助くる者を助く」
3つ目の名言は、「天は自ら助くる者を助く」です。
直訳すると、「天は自分自身で努力する人を助ける」という意味です。
もう少し分かりやすい言葉で説明すると、他人の力に頼らず自分の力で何とかしようと頑張る人は、天が助けてくれる、ってことですね。
手紙屋は、これを会社で働くサラリーマンに例えて説明してくれます。
サラリーマンの頑張りの成果は、人それぞれです。一人で数人分の働きをするサラリーマンもいれば、手を抜いて仕事をするサラリーマンもいます。頑張るレベルは大きく違いますが、給料としては大きな差が生まれません。
「私はこんなに頑張っているのに、どうして…」
と愚痴を言いたくなること、ありますよね。
そんな時でも、手紙屋は、
手を抜く人生を選ばないのが大切
と教えてくれます。
”『平時はあなたの頑張りで他の社員の分まで給料を稼ぎ出す』”
いつもは、他人の分まで自分が稼ぐ。こんなにかっこいいことは無い。
会社は、そんな他人の分まで身を粉にして頑張る人を評価し、会社側の人間、つまり出世させます。
いつも会社側が正しく頑張る人を評価するとは限らないのが悲しいところですが、いつも頑張っていれば、いつかはきっと正しく評価してくれる人が現れる、と信じたいですね。
「天は自ら助くる者を助く」: 他人の力に頼らず、自分の力で頑張る。そんな人を天はちゃんと見ていてくれる。
(4)「思いどおりの人生を送る」
4つ目の名言は、「思いどおりの人生を送る」です。
手紙屋は、人間には二種類の人間が存在すると言います。
”『人生は思いどおりにいく』 多くの成功者が座右の銘にする言葉です。 『人生は思いどおりにいかない』 夢を実現できなかった、もっと多くの人たちが感じる人生の教訓です。”
- 「人生は思いどおりにいく」と思うのが成功者。
- 「人生は思いどおりにいかない」と思うのが夢を実現できなかった人たち。
そうですね。「人生は思いどおりにいきますねぇ」なんて言う人に出会ったことがない、というのが正直な感想です。
しかし、手紙屋は、
「人生は思いどおりにいく」
と断言します。
その理由を、「頭の中に”天秤”を用意する」ことの例え話で、分かりやすく説明してくれます。
<天秤の話>
”それは、あなたの頭の中にいつも〝天秤〟を用意することです。”
例えば、チームで一番野球がうまくなりたい少年がいたとします。
この少年は、現時点では、チームの中でまだまだ下手くそな方です。
手紙屋の名言の1つ目で紹介した「物々交換」をしようとすると、当然のように成立しません。
そこで、頭の中に天秤を思い浮かべます。
- 片方の皿に「チームで一番うまい野球選手」
- もう片方の皿に「少年の努力の量」
を載せます。
あなたの頭の中で天秤を思い描くと、手に入れられる物と、手に入れられない物を、正確に判断することができます。
天秤を頭に思い描くと、今の努力の量では一番になれるはずがない、と瞬時に理解できますもんね。
これができないと、「ボクには運が無い」と、いつまでたっても夢を実現できない大人になってしまうのです。
ちなみに、この「天秤」の話は、喜多川泰さんの他の作品にも出てきますね。例えば、「秘密結社Ladybirdと僕の6日間」にも出てきます。Ladybirdの発案者の二階堂肇が言う名言ですね。こちらの本もとても感動するので、是非読んでみてください。
思いどおりの人生を送る」: 頭の中に「天秤」を思い描く。片方の皿に欲しい物を。もう片方の皿に自分が積み重ねた努力を置く。天秤が釣り合うとき、はじめて欲しいものが手に入る。思いどおりの人生を送ることができるようになる。
(5)「ある人の人生」
手紙屋の名言、5つ目は「ある人の人生」です。
ここで言う「ある人」とは、「法人」つまり「会社」のことです。
手紙屋は、会社の人生について語ります。
私たちは、会社の人生ってどんなだろう? と思いをはせたこと、ありませんよね。私もありません。しかし、手紙屋は言います。会社の人生を理解すると、「働く」ことの本質が見えてくる、と。
会社は、生きていくために2つのことを達成しなければいけない、と、手紙屋は言います。
”『多くの人から長期間にわたって必要とされ続けること』 そして、もう一つは 『収入内の生活をすること』”
管理人なりにかみ砕いて解釈すると、
- 人に必要とされること
- お金を稼ぐこと
となります。
人に必要とされることも、生活をする上で最低限のお金を稼ぐことも、人間も会社も同じであることが分かります。
つまり、会社を選ぶときも同じ。お金をもらうことも大切だけど、実は生活に必要な最低限のお金さえあれば生きていけます。それよりも、「人に必要とされること」。これが大切。会社を選ぶとき、給料や仕事が楽そうかだけで選んでいませんか?
- 自分はどんなことで人の役に立てるだろう?
- 自分はどんなことを人にしてあげると幸せに感じるのだろう?
そんなことを考えて仕事を選ぶとよいかもしれませんね。
「ある人の人生」: 会社の一生も人間の一生とよく似ている。人の役に立つ。これを忘れなければ豊かな人生を送ることができる。
(6)「自分に向いていることを探さない」
手紙屋の名言、6つ目は「自分に向いていることを探さない」です。
あなたがまだ働いたこともない、経験の少ない人であれば、そもそも自分に向いていることを知っているはずがないと言います。
言われてみれば、その通りですよね。
生まれてから子供時代を経て、小学校、中学校、高校、大学と、学校生活では確かに経験を積みます。でも、学校生活と社会人生活とでは、やはり違う。というのが根本にあります。
学校生活での経験は、もちろん素晴らしく、かけがえのないものです。でも、それだけで「自分にはこの仕事が向いている!」を決めつけるのは、時期尚早である。というのが手紙屋の意見です。
初めは誰でも自分に向いている仕事は分からないのは当然。いろんな仕事を経験して、自分に向いている仕事をゆっくり探せばOK!
”どんな会社に就職したとしても、それは自分でつくり始める人生の入り口にすぎません。 向いている職業を探すのはやめて、興味が持てる会社を探してみてください。”
こんな言葉を就職活動の時に聞けたらどんなに心が楽になったか。と思ってしまう管理人でした。
「自分に向いていることを探さない」: 初めは誰だって自分に何が向いているのかなんて分からない。それよりも、自分が少しでも興味を持てる会社を探すのがいい。
(7)「急がば回れ」
手紙屋の名言、7つ目は「急がば回れ」です。
”人が夢や目標を持つと、目の前には必ず壁が現れます。”
人は、普段なにも考えずに生活していると気付かないけど、夢や目標を持つと、いつの間にか目の前に壁が現れていることに気付きます。
その壁を乗り越えることはもちろん大事ですが、どんな手段を使っても乗り越えればよい、という訳ではありません。
その壁を「どのように」乗り越えるか。それが大事だと手紙屋は言います。
仮にその壁が自分の将来に必要とは思えない壁だったとします。
例えば、学校生活での数学の勉強。数学を苦手とする人は、口々にこう言います。
「私は将来、理系の仕事には就かないから、数学は勉強しなくても全く困らない」と。
しかし、その考え方では夢をつかむことはできないと、手紙屋は言います。
”『今、目の前にあるものに全力を注いで生きる』”
さらに、手紙屋は続けます。
”目の前に現れる壁は、一見あなたにとって必要なさそうなものに見えても、自分が進もうとする人生にどうしても必要だから現れるのです。”
目の前に現れた壁は、あなたに必要であるから現れる。
こんなこと考えたことはありませんが、もしそうだとすると、どんな壁も自分の人生において、意味のある壁なんだ、と思えて頑張る気持ちが芽生えます。
今までは、「こんなことして意味ないじゃん」と思っていたことが、急に「ワシの人生に無くてはならない壁」と考えが180度変わりますね。
「急がば回れ」: 目の前に現れる壁は、あなたの人生にとってなくてはならない壁。どんな壁も逃げずに立ち向かう姿勢でいれば、あなたの人生は成功したも同然!
(8)「あなたの成功は世界を変える」
手紙屋の名言、8つ目は「あなたの成功は世界を変える」です。
”一人でも多くの人から必要とされるのを目標にすることは、何よりも重要”
多くの人から必要とされるのを目標にする。
”それは自分のやりたいことが、一見、世の中の誰も実現できそうにないことであっても、絶対に、「これは無理だから……」と自分の中から切り捨てないことです。”
大きな目標を持つことを恐れない。怖がらない。
”乗り越えられる壁しかあなたの前には現れてこないのです。”
この言葉は、とても心強いですね。乗り越えられる壁しか、あなたの前には現れない。
”わたしは、若い人たちに「できるだけ大きな壁を、たくさん越える生き方をしなさい」と言ってあげたほうがいいと思うんです。”
大きな夢を持つことと、大きな壁を乗り越えることは同じ。
大きな壁を越え続け、あなたが成功し続けることで、多くの人に必要とされる存在になる。
そして、あなたの成功は、世界を変える。
「あなたの成功は世界を変える」: 多くの人に必要とされる存在になり、あなたの大応援団ができる。世界を変える存在になる。
(9)「自分を磨き、行動する」
手紙屋の名言、9つ目は「自分を磨き、行動する」。
手紙屋は、行動し続けるには、「習慣化」するのがよいと言います。
”それを習慣化するのです。 私との文通を、ではないですよ。 誰かの考えが記されているものを読み、それに対する自分の意見を書く、という作業を習慣化することです。”
知見を広め、それを自分の言葉にして理解する。それを習慣化する。
動き続けることが大切。
この考え方は、喜多川泰さんの「賢者の書」でも出てきましたね。第1の賢者アクトの名言です。(「賢者の書」の名言)
ポイント:「自分を磨き、行動する」: 知見を広め、自分を磨き、それを習慣化する。
(10)「人生の始まり」
手紙屋の名言、涼太の就職活動編の最後は、「人生の始まり」です。
手紙屋は、「成功する人」と「失敗する人」との違いを、次のように表現します。
失敗する人:
”『私には才能がなかった』”
成功する人:
”『どうしてもやりたいことを、情熱をもって続けてきただけです』”
- 失敗する人は、才能を頼りに夢をかなえようとした。
- 成功する人は、努力の量を頼りに夢をかなえようとした。
その通り。自分の欲しい物を手に入れるには、天秤を頭に思い描く。
片方の皿には、自分の欲しい物を。もう片方の皿には、その欲しい物に見合う努力の量を。
あなたの努力が欲しい物と釣り合う時、初めてその欲しい物は手に入ります。
努力を継続すること。
それさえできれば、成功する人生の始まりと言っても過言ではありません。
「人生の始まり」: 頭の中に天秤を思い描き、欲しい物に等しい努力を継続する。それさえできれば成功を手に入れられる。
【番外編】喜太朗の名言
ここで、涼太の就職活動編に出てくる手紙屋以外の名言として、涼太の姉の夫にあたる喜太朗(よしたろう)さんの名言を紹介します。
”「倒れなかった者が強いんじゃなくて、倒れても立ち上がる者が本当に強いんだよ」”
これは、手紙屋の4通目の手紙を受け取る前に、喜太朗から涼太へ贈られた言葉です。
人は、初めから強くなくてもいい。倒れてもまた立ち上がる勇気さえあれば、それでいい。
そう言われているような気がして、少し気持ちが楽になるのと同時に、倒れてもまた立ち上がろう! と背中をひと押ししてくれる、素晴らしい名言です。
和花の受験勉強編
手紙屋の名言_和花の受験勉強編.jpg)
ここからは、「手紙屋」の2作目「手紙屋 蛍雪篇 私の受験勉強を変えた十通の手紙」より、手紙屋の名言をお届けします。
2作目の「和花の受験勉強編」は、タイトルの通り受験勉強に悩む高校3年生の和花が主人公の物語です。時は、1作目から4年前にさかのぼります。では、「和花の受験勉強編」の名言をお楽しみください。
(1)「勉強も一つの道具である」
和花との1通目の手紙で、手紙屋はこう言います。
”これからしばらくの間、勉強するのをやめてほしいのです。”
手紙屋は、その理由をこう言います。
嫌々やっても勉強しないのと同じ
だと。
そして、いつまで勉強するのをやめてほしいのかと言うと、和花が勉強したくてしたくて我慢できなくなるまで、と。
そして、手紙屋は勉強について、独自の哲学を語ります。
”私は、勉強は一つの道具にすぎないと思っています。
ですから、「やらないよりは、やったほうがいいだろう」という考え方は間違っていると思うんです。”
道具は、正しい使い方をして、初めて役に立つもの。
誤った使い方をしては、逆効果である。と言うのです。
”『何の目的のために、それを使おうとしているのか』”
それを知らずして「勉強」という道具を使うのは、よろしくない、と言います。
では、何のために勉強するのか?
その答えは、意外なものでした。続きは、是非、本でお楽しみください。
「勉強も一つの道具にすぎない」: 勉強は、何のためにするのか? それを理解して使わないと意味が無い。
(2)「学校で習うことだけが勉強ではない」
こちらは分かりやすい言葉ですね。
本当にその通りで、学校で習うことだけが勉強ではありません。
社会人になり、仕事に就くと、学校の勉強以外のことを、毎日のように覚えていかなければいけません。
ただし、学校の勉強より、その勉強の目的がわかりやすいという意味で、社会人になってからの勉強の方が、苦にならないような気もしますね。
(3)「心の成長なくして、結果を手にすることはできない」
和花へ贈る手紙屋の名言、3つ目は「心の成長なくして、結果を手にすることはできない」です。
手紙屋がここで言う「心の成長」とは、
道具としての「勉強」をどのように使うのかを、自分できちんと理解すること
です。
例えば、道具としての「勉強」を、「一流大学の受験に合格するため」だけに使ってしまえば、これは正しい使い方とは言えません。もし、一流大学の受験に合格しても、その後の大学生活を目標なく過ごしてしまっては意味がありません。
さらに、もし一流大学の受験に不合格という結果になってしまったら、勉強すること自体に不信感を持ってしまい、勉強嫌いにもなりえます。
逆に、道具としての「勉強」を正しく使った場合はどうでしょう。
「勉強」を「一流大学の受験に合格するため」ではなく、「将来、〇〇の仕事をして人の役に立ちたいから、△△を学べるこの大学に入りたい」ために使うのであれば、正しい使い方と言えるのではないでしょうか。大学のブランドを目的にしなければ、学べる大学はその大学以外にもたくさんあるのですから。
(4)「自分が生きる意味は、自分でつくっていける」
和花へ贈る手紙屋の名言、4つ目は「自分が生きる意味は、自分でつくっていける」です。
”『自分は何のために存在するのだろう?』”
若い人は、この悩みにいつの日か出会うことになります。
その答えは、良い経験、悪い経験、様々な経験を積むことで自ずと導き出されます。
”自らを磨いて、何かの役に立てたときにはじめて、人生に意味が生まれたと自覚できます。”
学校生活でも、社会人生活でも、誰かの役に立って、「ありがとう」と心からお礼を言われる。そんな経験をすると、お金では買えない、何とも言えない充実感を味わえます。
「自分が生きる意味は、自分でつくっていける」
その通りだと思います。あなたが何かの役に立つために行動することで、自分の生きる意味は後からついて来る、ということですね。
(5)「困難を可能にするのは「意志」の力」
和花へ贈る手紙屋の5つ目の名言は「困難を可能にするのは「意志」の力」です。
「意志力」は本当に大事だと思います。
ただ、今回ばかりは、手紙屋の意見に賛同できない点があります。
”『「意志」の力を強く持ちつづけるために、「勉強」という道具を使う』”
手紙屋は、意志力のために、つまり継続するために「勉強」を道具として使う、と言いますが、これができないんですよね。
そこで、「意志力」の権威、ロイ・バウマイスターの登場です。ロイ・バウマイスターは、「意志力は、筋肉と同じ」と言います。つまり、意志力は正しいトレーニングを積めば、筋肉みたく鍛えられる、と。また、意志力は、体力と同じように使えば消耗します。意志力の消耗を抑えるにはどうしたらよいか?
最も効果的なのが、「習慣化」です。意志力を使わずとも、自動でこなしてしまう。それが習慣化。習慣化するポイントは、「21日間続ける」。これが重要!
はじめは、
これ続ける意味あるの?
と思ってしまうほど、ハードルを下げた目標をかかげ、それを21日間、何がなんでも続けます。これをクリアできれば、あとは徐々に目標とするハードルを上げ、習慣化する物ごとのレベルを上げていきます。
ちょっと話がそれましたが、手紙屋の言う「困難を可能にするのは意志」には、同意です。
ここで、少し当ブログの宣伝です。
「意志力」について、詳しくまとめたページは、こちら↓
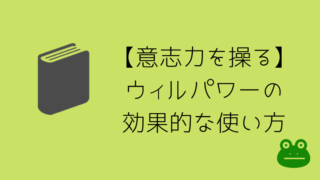
「習慣化」について、詳しくまとめたページは、こちら↓

(6)「成功するために必要なものは、方法ではなく行動だ」
和花へ贈る手紙屋の名言、6つ目は「成功するために必要なものは、方法ではなく行動だ」です。
成功するためのヒントが書かれた本を読んで、
なるほど!
と納得して、それで満足して終わってしまう。
つまり、成功する方法だけ学んで、行動しない。
それでは成功しませんよね。
本から知識を得ることはもちろん大事ですが、それ以上に重要なのが「行動」。
思い立ったときに行動できるかどうかが、成功の秘訣だったのです。
なお、この「行動」が大事であることは、1作目の手紙屋でも触れていますね。9つ目の名言で「自分を磨き、行動する」と書かれています。
(7)「家に帰ってから最初に座る場所で、自分の人生が決まる」
和花へ贈る手紙屋の名言、7つ目は「家に帰ってから最初に座る場所で、自分の人生が決まる」です。
学校生活でも、社会人生活でも、家に帰ればとりあえずくつろぎたいですよね。
そこを「家に帰っても、くつろぐべからず!」と唱えるのは手紙屋。
かなり手厳しい一言ですね。
手紙屋は言います。
”大切なのは、最初に座る場所をあなたが勉強する場所にすること。”
勉強さえ始めてしまえば、5分でもいい。と言います。
人は、行動し始めさえすれば、ある程度は集中して作業できるという人間の特性をついたもののようです。
これも5通目の手紙と同じで、「習慣化」が鍵を握りますね。
一度、「帰宅したら勉強机に向かう」を習慣化できれば、あとは苦労することなく続けられます。初めのうちは、難しい勉強ではなく簡単な勉強を。もっというと、勉強でなくても、例えば本を読む、でもいいですね。習慣化できるまでは、ハードルは極限まで下げてしまいましょう。
(8)「「何をやるか」よりもっと大切なことがある」
和花へ贈る手紙屋の名言、8つ目は「「何をやるか」よりもっと大切なことがある」です。
手紙屋は言います。
”あなたが考えなければならないのは、「何を」ということよりも、「どう」やるかなのです。”
どうやるか、が大事。
ただ漫然と数学の問題を何十問と解いていても、そのうち飽きてしまうのは目に見えて明らかです。
そうではなく、この問題を解いた後、どうしようか?
例えば、このくらい難しい問題であれば、お父さんでも解けないだろう。よし、自分が解けるようになった後で、お父さんに「この問題、解ける?」と聞いてみよう。もし、お父さんが解けなかったら、ついに私はお父さんを越えたのだ。と言えるぞ。イヒヒ。
この問題が解けるようになったら、次はどうする?
それを考えながら勉強すると、案外飽きずに勉強できるかもしれません。
(9)「すべての教科が、人生を豊かにするきっかけになる」
和花へ贈る手紙屋の名言、9つ目は「すべての教科が、人生を豊かにするきっかけになる」です。
手紙屋は、これは必要でこれは必要ない、という考え方はNGと言います。
”今の自分が持っている狭い興味の中でしか自分の能力を発揮できないという生き方は不自由です。人間の能力のほんの一部分だけを使って生きていくことになるからです。”
つまり、今、興味のある教科しか勉強しないなんてもったいない。あなたの能力は、今、気づいていないだけで、実はそれ以外にも伸びる能力があるということ。
この手紙屋の意見についても、同意できる部分もあるけど、同意しかねる部分もあります。
管理人が思うのはこうです。
人生は短い。人生の中でできる時間は限られている。だったら、その限られた時間を自分の興味のあることにつぎ込むべき。ただし、目の前に現れる一見、自分の人生に不要と思える壁については、逃げずに乗り越えるべき。とも思います。なぜなら、その壁は自分の人生に必要だから現れたものだと信じているからです。例えば、気乗りしない会社の付き合いの飲み会。これは嫌なら避けても良いと思います。飲み会も人生の転機になることがあるかもしれませんが…。
(10)「今日一日の勉強が、将来の世界を大きく変える」
和花へ贈る手紙屋の名言、最後の名言は「今日一日の勉強が、将来の世界を大きく変える」です。
手紙屋は、誰かの役に立つために勉強を道具として使うことを忘れないで下さい、と言います。
”つまり、勉強という道具は、『自分を磨くため』『人の役に立つため』という二つの目的のために使ったときにはじめて、正しい使い方をしたといえるのです。”
自分を磨いて、人の役に立つ。
人生というのは、結局はここに行きつくのだと思います。
人の役に立つ。
そして、人の役に立ったことを実感したとき、自分も幸せな気持ちになれます。
社会に出て仕事をしていると実感しますよね。どんな些細な事でも、相手から「ありがとう」と一言をもらうだけで、この仕事をしていて良かった、と思えます。
さて、手紙屋の名言に戻りますと、壮大ですね。
「今日一日の勉強が、将来の世界を大きく変える」
手紙屋が伝えたいことは、あなたの勉強して手に入れた能力が、人の役に立つ仕事として発揮されたとき、それらの人々は幸せになれる。それを繰り返すことで、いずれは将来の世界を大きく変える。つまり、世界中を幸せにできる。
そのためには、まずははじめの一歩です。行動を起こす。
この「手紙屋」の本が、あなたの行動を起こす第一歩のきっかけになったら嬉しいです。
まとめ|「手紙屋」の名言

手紙屋の名言をお届けしました。いかがでしたでしょうか。
予想以上に大ボリュームになってしまいました。
手紙屋の名言をまとめよう! と思いついた時、「涼太の就職活動編」と「和花の受験勉強編」とで別々にまとめようと考えていました。
しかしながら、物語が繋がっていることと、著者である喜多川泰さんが同時に二冊を書きあげていた経緯を知ってしまうと、これは1つの名言としてまとめるべきだな、と考え直した次第です。
おかげで記事が大ボリュームになってしまいましたが、二つの作品を見比べることで見えてくるものもありました。
それは、喜多川泰さんが最も伝えたかったメッセージ。
受験勉強から就職活動にかけた時期は、人間が子供から大人になる最も大切な時期です。
そんな最も大切な時期に、自分とは何者なんだろう? と、誰もが答えのない壮大な悩みを抱えます。
その答えを「手紙屋」という作品を通して教えてくれます。
自分という人間の存在意義。それは、世界を変えるためにあなたは存在する。
ちょっと壮大すぎて、後ずさりしてしまいそうですが、そうなんです。
一作目の「手紙屋」(就職活動編)では、手紙屋からの8通目の手紙で「あなたの成功は世界を変える」と説いています。
二作目の「手紙屋」(受験勉強編)では、手紙屋からの10通目の手紙で「今日一日の勉強が、世界を変える」と説いています。
勉強すること、働くこと、どちらも自分が世界を変えることに通じているのです。
自分のした勉強が、仕事が、世界を変える。ワクワクしませんか?
「就職活動編」の名言、「受験勉強編」の名言、合わせて20個もありますが、何度も読み返して自分のものにできたら、素晴らしい人生になるような気がしてなりません。
「手紙屋」の本を何度も読み返して自分のものにしたい管理人より。
喜多川泰さんの「上京物語」も学びポイントが満載です↓

さらにこちらも喜多川泰さんの「秘密結社Ladybirdと僕の6日間」も人生の教訓満載です↓
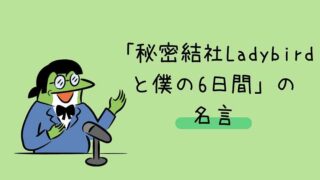
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。